債権回収代行とは?外部に依頼するメリットと進め方を解説
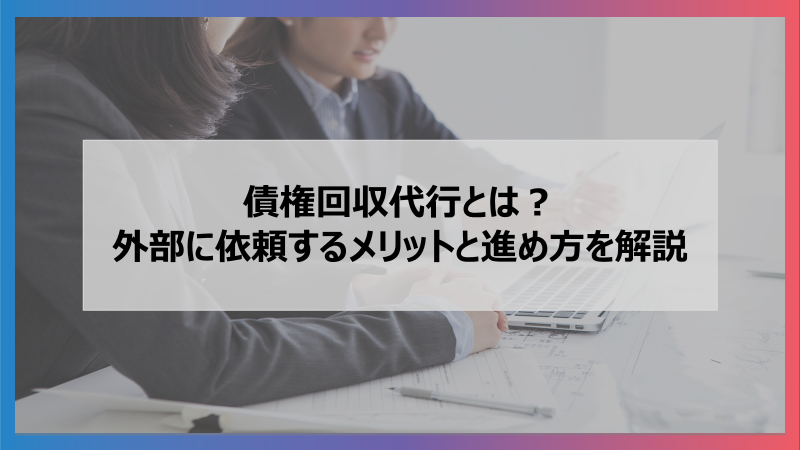
「お金を貸したけどなかなか返ってこない…」 「回収に時間と労力をかけたくない…」そんな悩みはありませんか?債権回収代行は、債権回収の専門家に依頼することで、回収業務を効率的に進め、債権回収の可能性を高める手段です。 本記事では、債権回収代行を検討すべきケースや、依頼するメリット、回収の進め方について解説します。
債権回収代行とは?
一般的に「債権回収代行」と呼ばれていますが、法律上は「債権管理回収業」といいます。弁護士やその他の事業者が、委託または譲渡された「特定金銭債権」の回収や管理を行う事業のことです。弁護士以外の事業者は、「サービサー法」と呼ばれる法律に基づき、この特定金銭債権のみを取り扱うことができます。
特定金銭債権には、以下のようなものが該当します。
- 金融機関が所有している、所有していた貸付債権
- リースやクレジットの債権
- ファクタリング業者が有する金銭債権
- 資産の流動化に関する金銭債権
- 法的倒産手続き中の企業が有する金銭債権
- 保険契約に基づく債権 など
サービサー法
サービサー法とは、債権回収会社が金融機関等から委託、または譲り受けて特定金銭債権の管理・回収を行うことです。平成10年に公布、平成11年に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法」によって、従来は弁護士のみが行っていた債権管理回収業務が、法務大臣の許可制となりました。
この法律の目的は不良債権の処理を促進し、より円滑な債権回収を図るためです。民間企業による債権管理回収業務の解禁により債権回収市場の活性化が期待されます。反社会的勢力の参入を防ぐための仕組みを導入し、許可を受けた業者に対しては必要な規制と監督が行わるため、債権回収の過程における不正行為を防ぎ、債権者と債務者の双方にとってより公正な取引環境が実現されました。
債権回収代行を業者に依頼すべきケース
債権回収は自社で行うことも可能ですが、専門的な知識やノウハウが必要なので、多くの企業は債権回収代行業者に依頼することがほとんどです。
債権回収代行を専門業者に依頼すべきケースは、大きく2つに分けられます。
自社のリソースが不足している場合
債権回収には法律知識や交渉力・時間・労力が必要なため、これらのリソースが不足している場合は専門業者に依頼することをおすすめします。専門業者に依頼をすることで豊富な経験と実績に基づき債務者との交渉や法的対応を円滑に進めることができ、効率的かつスムーズな回収が可能になります。
専門的な知識やスキルが必要な場合
債権回収は、民法や商法・債権回収法などの法律知識が求まられますので、特に複雑な債権回収案件や裁判手続きが必要な案件などは、専門的な知識を持つ業者に依頼する方が良いでしょう。専門業者は、法的な手続きや書類作成に精通しており、債権回収を円滑に進めるための適切なアドバイスやサポートが可能です。
また、取引先が意図的に支払いを拒否している場合は、弁護士などの専門家に債権回収を依頼しましょう。弁護士を介することで、取引先に対して法的な手段をとることが可能となりスムーズな回収が期待できます。弁護士を相手にすることに躊躇する取引先も、法的な対応には慎重になるため、早期の解決につながる可能性があります。
債権回収代行を依頼できる業者
債権回収の代行を依頼できる業者は大きく3つのカテゴリーに分類されます。
- 債権回収会社(サービサー)
- ファクタリング会社
- 債権回収に特化した弁護士
それぞれの専門性の違いや、依頼するメリットとデメリットを詳しく解説します。
債権回収会社(サービサー)
冒頭でご説明した通り、債権回収会社は債務者から債権を回収することを代行する専門業者です。
メリットは、未回収債権を確実に資産化できる点です。債権回収会社に依頼する場合、債権を買い取ってもらう形となるため、弁護士に依頼する場合と異なり、費用倒れになるリスクがありません。
デメリットは、依頼できる債権者が限られる点です。扱うことができる債権には制限があり、金融機関など一部に限られています。もう一点は回収金額が少なくなる点です。一般的に債権の買取価格は、債権の実際の価格よりも低く設定されており、債権を全額回収できた場合と比較して、回収金額が少なくなる可能性があります。
ファクタリング会社
売掛債権の買い取りによって資金調達を支援するファクタリング会社は、金融機関が主体として運営されています。ファクタリング会社に依頼する際は、債権回収会社と同様に債権の売却を依頼することになります。
関連記事:ファクタリングとは?種類や手数料の相場、利用する際の注意点を解説
ファクタリングのメリットは、未回収分の債権を確実に資産化できる点です。
デメリットは手続きに費用が発生してしまう点です。ファクタリング会社は主に取引先からの債権の売却に対応しており、売却時には債権額の10〜20%程度の手数料が発生するのが一般的です。また、債権の売却が不可能な場合や、ファクタリング会社が債務者への回収対応を行うための手続き費用が発生する場合もあり、依頼前に十分な確認が必要です。
弁護士
弁護士のメリットは、多岐にわたる手続きの代行を専門に行うことができる点です。例えば、弁護士名義の書類通知や債務者との交渉、裁判書類の作成、裁判への出廷など、債権回収に必要な業務を依頼することで、債権者側の負担を大幅に軽減できます。さらに、弁護士は債権回収の専門家として、状況に応じた適切な回収方法を提案し、債権の種類や状況に応じて、多角的なサポートを提供することも可能です。
デメリットは、弁護士費用が債権回収額を上回る可能性がある点です。弁護士は債権の買い取りではなく、あくまで「債権回収のためのサポート」です。依頼時には、着手金や成功報酬などの弁護士費用が発生し、場合によっては当初の予定になかった追加手続きが発生する可能性もあり、その際には別途オプション料金が発生することがあります。弁護士費用は、依頼内容や手続きによって大きく変動するため、費用倒れになる可能性もあります。
債権回収代行による取り立ての進め方
債権回収代行による取り立ての進め方はさまざまな方法があります。ここでは、債務者との交渉から訴訟まで、債権回収における4つの一般的なプロセスについて詳しく解説します。
1. 債務者との交渉
債権回収の最初の段階では、債務者との円滑なコミュニケーションが重要となるため、まずは穏便な方法で、返済の意向を確認し、返済計画を策定します。電話、手紙、メールなど、さまざまな手段で債務者と連絡を取り状況を把握し、債務者との交渉経験が豊富な専門スタッフが相手の立場を理解し柔軟に対応します。
2. 督促状の送付
債務者との交渉がうまく進まない場合は、督促状を送付します。督促状は、債権回収代行会社から債務者に送付され、返済を強く求める内容が記載されています。送達されたことを証明するために、内容証明郵便で送付される場合があります。
3. 裁判外での和解交渉
督促状を送付後も返済が見られない場合は、裁判よりもより迅速に解決するために裁判外での和解交渉を行います。裁判外での和解交渉では、債務者と債権者、または債権回収代行会社が話し合いを行い、返済方法や返済金額などを決定します。弁護士などの専門家のサポートを受けることで、より円滑に進めることができます。
4. 訴訟
裁判外での和解交渉が不調に終わった場合は、訴訟という手段をとることも考えられます。訴訟では裁判所に返済を求める訴えを起こし、裁判所の判決によって返済を強制することが可能ですが、裁判外での和解交渉よりも費用がかかります。
まとめ
債権回収は、時間と労力を要するだけでなく、精神的な負担も大きいため、自社で対応するのが難しいケースも多いです。専門的な知識や経験を持つプロが、債務者との交渉や法的手続きを代行することで、債権回収の成功率を高め、時間や精神的な負担を軽減します。
回収不能と諦めていた債権も、専門家に見てもらうことで回収できる可能性があります。債権回収でお困りの際は、債権回収代行を検討してみてください。
-
債権回収代行はどのような回収方法がありますか?
債権回収代行には、様々な方法があります。主な回収方法は、以下の通りです。
・書面による督促: 債務者に支払いを督促する手紙を送付します。内容証明郵便など、法的効力を持つ方法もあります。
・電話による督促: 電話で債務者に支払いを督促します。直接的なコミュニケーションを通じて、支払いの意向を確認することができます。
・訪問による督促: 債務者の会社や自宅を訪問して、支払いを督促します。直接交渉することで、より効果的に支払いを促すことができます。
・法的措置: 訴訟や差押えなどの法的措置を検討します。債務者が支払いを拒否した場合に有効な手段です。
-
債権回収代行業者を選ぶ際の注意点はありますか?
債権回収代行業者を選ぶ際には、以下の点に注意する必要があります。
・実績: 多くの債権回収実績を持つ業者を選びましょう。
・費用: 費用体系や手数料などを事前に確認しましょう。
・対応エリア: 債務者の所在地域に対応している業者を選びましょう。
・評判: 過去の顧客からの評判などを参考にしましょう。
FUEL 編集部 TAKAHASHI
ターゲットメディア株式会社(2018年入社)運用ディレクター。
広告・マーケティング業界に特化したBtoBメディアの運用責任者を経て
育児のため一時休職。現在は、中小企業向けの情報サイト「FUEL」の運用に従事。