請求代行サービスとは?任せられる業務範囲と外注先の選び方
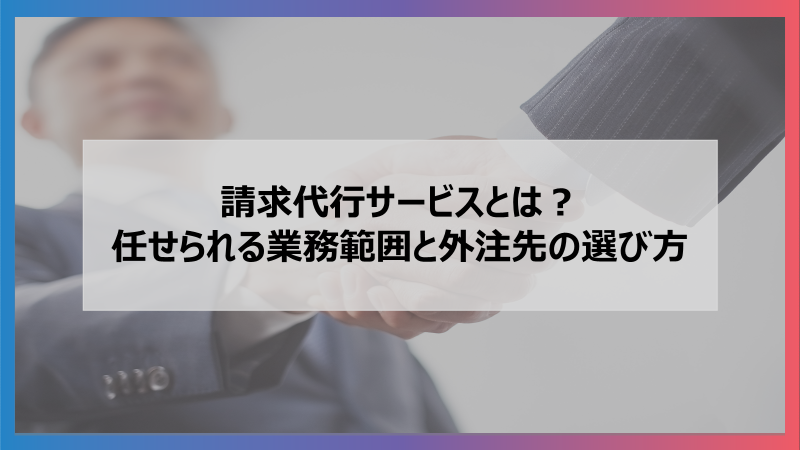
「請求業務は面倒で時間がかかる」「未回収金の心配がある」とお悩みではありませんか? 請求代行サービスは、企業間取引における請求業務を代行するサービスです。請求代行サービスを利用することで、請求書作成から発送、入金管理までを専門業者に任せることができ、自社の業務に集中できます。 さらに、未回収金発生のリスクを軽減し、資金繰り安定化にもつながります。 本記事では、請求代行サービスの業務範囲やメリットデメリット、選び方のポイントを詳しく解説します。 請求業務の効率化、資金繰り安定化を目指したい方は、ぜひ参考にしてください。
請求代行サービスで任せられる業務範囲とメリット
請求代行サービスとは、請求書の作成から発送まで請求に関わる業務を代行してくれるサービスです。ここでは、主に委託できる業務内容は解説します。
請求書作成・発行業務
請求書の作成や発行業務は、難易度が高いわけではありませんが、取引先が増えるにつれて時間や工数がかかる業務です。また、取引先によって請求時期や請求フォーマットが異なることもあるため、ミスや請求漏れなどにつながるケースもあります。
請求代行サービスを利用することで、請求業務を委託できるため、業務負担やミスを減らすことが期待できます。
入金確認業務
請求書を発行したら、期日までに請求金額が指定の口座に振り込まれているかを確認する必要があります。また、入金確認後には、売掛金のデータを取り消す消込作業を行う必要があります。こうした入金管理業務も件数が増えるほど手間もかかります。
この入金管理業務も請求代行サービスに委託することが可能です。
督促・代金回収業務
期日までに入金が確認できない場合は、取引先に対して支払いを督促する必要があります。督促業務は、経理担当者にとってストレスのかかる業務です。請求代行サービスを利用することで、督促や代金回収を代行してくれるため、精神的負担を軽減できます。
請求代行サービスの中には、代金回収を代行してくれるだけでなく、未回収が発生した場合はその全額を保証してくれるサービスを提供しているところもあります。万が一、取引先が倒産したりして代金の回収ができなくなった場合でも安心です。
与信審査業務
与信審査は、取引先や顧客の経済状況や支払い能力を評価し、取引条件や与信限度額を決定する重要な業務です。しかし、中小企業の場合「どうやって調べたいいか分からない」ということも多いのではないでしょうか?
請求代行サービスの中には、こうした与信審査を委託できるサービスもあります。
請求代行サービスのデメリットはあるのか?
ここまで見ると請求代行サービスの利用はメリットしかないように感じますが、デメリットもあります。請求代行サービスを利用する場合は、以下の点も考慮して検討する必要があります。
費用が継続的にかかる
請求代行サービスを利用する場合は、当然のことながら費用が発生します。初期導入にかかる費用だけでなく、一請求あたりかかる代行手数料や代金回収の保証料、毎月の固定費などのコストがかかります。
<請求代行サービスにかかる費用項目>
| 費用項目 | 補足説明 | 費用相場 |
| 初期費用 | サービス導入時にかかる初期費用 | 最近のサービスは無料が多い |
| 月額費用 | サービス利用時にかかる固定費 | 無料~数万円 |
| 手数料 | 請求業務の代行件数ごとに発生する費用 | 1請求代行あたり0.5%〜5.5%程度 |
請求代行サービスの多くは初期費用が無料ですが、月額料金や手数料はサービスごとに違いがあります。月額費用が無料のサービスもありますが、その場合は手数料が比較的に高くなる傾向があります。
そのため自社の事業や取引形態を踏まえて、「どの料金体系が「最もコストを抑えられそうか」を考えたうえで判断していきましょう。
ノウハウの蓄積が不足する
請求代行サービスは、請求業務の効率化に役立ちますが、請求業務に関するノウハウを蓄積する機会を失う可能性もあります。
請求業務を外部に委託すると、自社内での請求業務経験が不足し、請求に関する知識やスキルの習得が遅れてしまう可能性があります。そのため、担当者が不在になった場合、業務を引き継ぐことが困難になるケースも考えられます。
請求業務に関するノウハウを社内に蓄積するには、以下のような対策が有効です。
- 請求代行サービスの利用範囲を限定し、一部の業務は自社で行うようにする
- 複数人で請求業務を分担し、担当者を複数確保することで、担当者の不在時でも業務を継続できるようにする
請求代行サービスを活用しながらも、自社内で請求業務の一部を担うことで、従業員のスキルアップを図り、将来的な業務継続性を確保することが重要です。
請求代行サービスを選ぶポイント
請求代行サービスを外部に委託する際には、いくつかの重要な要素を考慮する必要があります。
業種・ビジネスモデルに合致しているか
請求代行サービスを選ぶ際には、自社の事業内容やビジネスモデルとの適合性を慎重に検討することが大切です。すべての請求代行サービスが、あらゆる業種やビジネスモデルに対応しているわけではありません。
例えば、近年のビジネスモデルとして注目されているサブスクリプションやリカーリングビジネスなど、継続的な課金モデルに特化したサービスには対応していない請求代行サービスもあります。
事業拡大を目指している企業やスタートアップ、ベンチャー企業などは、将来的なビジネスモデルの変化にも対応できる柔軟なサービスを選ぶことが重要です。将来的に新しいビジネスモデルへの展開を検討している場合は、その対応能力も事前に確認しておきましょう。
請求書発行以外の業務も対応しているか
請求書発行以外にも、請求書関連業務の代行を依頼できるか調べる必要があります。請求書作成代行サービスによっては、代行範囲が請求書発行に限定されている場合があり、業務効率化の効果が十分に得られない可能性があります。
取引先が多い場合は、入金管理や回収代行、督促業務、与信管理などの業務を代行してくれるサービスを選ぶことで、大幅な業務負担軽減が期待できます。さらに、万が一のトラブルに備え、追加料金や対応時間などの詳細を事前に確認しておくと安心です。
既存システムとの連携が可能か
顧客管理システム、営業支援システム、会計ソフトといった企業が独自に導入しているシステムと連携できるかも確認しておきましょう。
今すぐ連携かが必要でない場合でも、こうした他の業務システムとの連携により、業務効率の大幅な改善が期待できるからです。
審査基準・与信額上限を確認
請求代行サービスは、与信審査のタイミングや与信額の上限によって、提供内容が異なります。企業は、自社の商品やサービスに最適なサービスを選択することが重要です。
与信審査のタイミングは、取引開始前に審査を行うか、取引発生後に審査を行うかの2つの方法があります。継続的な取引を目的とする場合、取引前の事前審査が有効です。一方、単発的な取引が多い場合は、受注案件ごとに審査を行うのが適しています。
与信額の上限は、取引先の購買意欲と与信額のバランスが重要です。取引規模に見合った与信額が設定されていれば、期間損失を防ぐことができます。ただし、新興企業や個人事業者など、信用度の低い取引先の場合、与信額の上限が低く設定されることがあります。
まとめ
請求業務代行サービスは、人手不足や業務効率化、未回収リスクの軽減など、様々な課題を抱える企業にとって有効な手段です。専門性の高い代行会社に業務を委託することで、請求業務にかかる時間とコストを削減し、営業活動や事業戦略に集中できる環境を構築できます。自社の状況に合わせて最適なサービスを選び、請求業務の効率化を実現しましょう。
-
請求代行サービスを利用しても、インボイス制度に対応できますか?
請求代行サービスを利用しても、インボイス制度に対応できます。ただ、利用を検討している請求代行サービスがインボイス制度に準拠した請求書発行に対応しているかは確認しましょう。
また、インボイス制度では、インボイス情報の保存が求められます。請求代行サービスがこれに対応したデータ保存機能を提供していると、その後の確認も楽になります。
-
請求代行サービスは個人事業主でも利用できますか?
請求代行サービスは個人事業主でも利用可能です。請求書の発行や支払い管理が効率化できるため、時間や手間を節約でき、特に業務が多忙な個人事業主にとって有用なサービスです。
FUEL 編集部 TAKAHASHI
ターゲットメディア株式会社(2018年入社)運用ディレクター。
広告・マーケティング業界に特化したBtoBメディアの運用責任者を経て
育児のため一時休職。現在は、中小企業向けの情報サイト「FUEL」の運用に従事。