請求書カード払いにすることで一時的な資金繰りを改善!
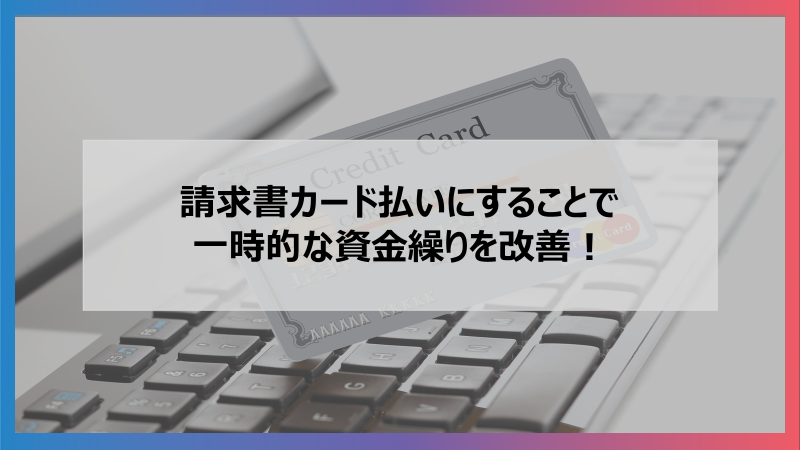
資金繰りを常に健全に保つことが重要なことはいうまでもないことですが、取引先からの入金タイミングがずれてしまったり、大きな支払いが迫っている場合、一時的な資金繰りが悪化してしまうことがあるかと思います。
こうした一時的な資金繰りの問題を解決するために、請求書をカード払いに切り替える企業が増えています。本記事では、請求書のカード払いを導入することで得られるキャッシュフローの改善効果や、導入にあたっての注意点なども併せてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
請求書のカード払いとは?
請求書カード払いとは、支払い代行サービスの一つです。
取引先からの請求書を請求書カード払いサービスに立て替え払いを依頼し、カード決済するものです。そのため、支払いの先延ばしをすることができます。支払いを延長できる期間は、利用するクレジットカードの支払いスケジュールによって異なります。
具体的な流れは以下の通りです:
1.取引先から請求書を受領
まず、通常通り取引先から請求書が発行されます。請求書の内容や金額、支払期限などは従来と同じです。
2.クレジットカード会社や決済サービスを通じて支払い
請求書をクレジットカードで支払う場合、請求書の支払い代行サービスや決済プラットフォームを利用します。例えば、クレジットカード対応の決済代行業者を通じて、取引先に対して支払いを実行します。決済代行業者が取引先に直接振込を行い、あなたはカード会社に後日、クレジットカードの請求として支払いを行う仕組みです。
3.カード会社への支払い
クレジットカードの締め日までに支払いが行われ、実際の現金の流出はカード会社への支払日まで延長されます。これにより、支払いを実質的に後ろ倒しにし、資金繰りに余裕を持たせることが可能です。
この流れにより、現金がすぐに必要になる場面でも資金繰りを柔軟に管理することができます。
どのくらい企業が導入している?
日本国内では、請求書の支払い方法としてクレジットカードの利用はまだ広く浸透しているとは言えませんが、中小企業や個人事業主を中心に普及してきています。
クレジットカード決済をサポートする請求書発行ツールや、オンライン決済サービスの登場により、従来の現金振込に代わる手段として注目が高まっています。
今後、日本においてもクレジットカードを活用した請求書払いはさらに拡大すると予想されています。特にデジタル化が進む中、ペーパーレスやリモートワークの促進に伴い、従来の手作業による銀行振込から、オンラインで簡単に管理できるカード払いが主流になる可能性が高いです。
政府や企業のキャッシュレス推進政策により、ビジネスのデジタル化が加速する中で、請求書カード払いは経費管理の面でも一層有効な選択肢となっていくと思われます。
請求書をクレジットカード払いにするメリット
資金繰りの改善
請求書をクレジットカードで支払う最大のメリットは、資金繰りの改善です。通常、請求書の支払いは銀行振込で行い、支払い期日が決められていますが、クレジットカードを利用することで支払いを実質的に先延ばしにすることが可能です。クレジットカードの支払い期日はカード会社の請求締め日と支払い日によって決まるため、支払期限を最大1〜2か月延ばすことができます。
この支払いサイトの延長により、手元の資金を長く保持できるため、キャッシュフローの管理が格段に楽になります。特に、急な出費が発生した場合でも、カード払いに切り替えることで即座に現金が出て行くのを防ぎ、資金調達や売掛金の回収までのタイムラグを埋めることができます。資金繰りが厳しい時期でも、カード払いを活用することで、短期的な資金不足を回避する手段として大きな役割を果たします。
ポイント還元やキャッシュバック
クレジットカードを利用することで得られるポイント還元やキャッシュバックも大きなメリットの一つです。一般的に、クレジットカードの利用に対して一定の割合でポイントが付与され、そのポイントを買い物やサービス利用に充てることができます。特に、企業や個人事業主が毎月大量の経費をカードで支払う場合、ポイントが大きな節約効果を生む可能性があります。
例えば、月に数百万円規模の請求書をカード払いにすることで、数万〜数十万円分のポイントやキャッシュバックを獲得できるケースもあります。これにより、実質的なコスト削減や経費の効率化が図れ、経営全体のコスト構造の改善にもつながります。
さらに、特定のクレジットカードでは、経営者向けに特化したキャッシュバックや優遇プログラムが提供されているため、ビジネス利用に適したカードを選ぶことで、さらなる利益を享受することが可能です。
支払いの管理が簡単になる
クレジットカードを使った支払いは、経理業務の効率化にも大きなメリットがあります。従来の銀行振込では、個別の取引ごとに振込手続きを行う必要があり、その都度確認作業や記録が必要です。しかし、カード払いでは取引が自動的に記録され、月末にクレジットカードの利用明細として一括で確認できるため、経理業務が簡素化されます。
また、クレジットカードを利用することで支払いの一元管理が可能となり、支払いの履歴を一括で確認できるため、各種経費の管理や精算作業もスムーズに行えます。これにより、取引先ごとの支払いや入金確認にかかる手間が減り、特に複数の支払いを一括で管理したい経営者や個人事業主にとっては、業務効率が大幅に向上します。
さらに、クラウド会計ソフトや経費管理ツールと連携することで、自動的にデータを取り込み、経費の仕分けや帳簿作成も簡単に行うことができるようになります。結果として、経理業務にかかる時間と労力が削減され、事業運営に集中する時間が増えるでしょう。
請求書クレジットカード払いのデメリットや注意点
手数料がかかる
請求書をクレジットカードで支払う際、最も気をつけなければならないのが手数料です。通常、クレジットカード決済には取引金額の数パーセントの手数料が発生します。これにより、現金や銀行振込と比べて、支払総額が増加する可能性があります。特に取引金額が大きい場合、手数料が経営コストに大きく影響するため、十分な注意が必要です。
クレジットカード会社が提供する特定の法人向けカードでは、手数料が優遇される場合があるため、カード選びも重要なポイントです。また、請求書払い代行サービスを利用することで、手数料の削減が可能な場合もあります。
カード限度額の注意点
クレジットカードには利用限度額が設定されており、取引額が大きくなるとその限度額に達してしまうリスクがあります。特に、複数の大口取引を一度にカードで支払う場合、限度額が不足して支払いができなくなる可能性があります。
対応していない事業者もある
すべての取引先がクレジットカード払いに対応しているわけではない点も注意が必要です。特に、中小企業や一部の伝統的な業種では、カード決済に対応していないことがまだ多く、請求書カード払いを希望しても、現金や振込のみを受け付けているケースがあります。
まず取引開始前や請求書発行時に、事前に取引先がクレジットカード決済に対応しているかを確認することが重要です。また、カード決済に対応していない取引先に対しては、カード払い代行サービスを利用することで、カード払いの恩恵を受けつつ、取引先は従来通り銀行振込を受け取ることができます。
請求書クレジットカード払いの導入方法
請求書のカード払いを導入するには、いくつかのステップを踏む必要があります。以下は、その基本的な手順です。
1.クレジットカード会社との契約
まず、請求書のカード払いを実現するためには、クレジットカード会社と契約する必要があります。多くのクレジットカード会社では、法人向けのクレジットカードやビジネスカードを提供しており、経費の支払いに特化した機能や特典が備わっています。ビジネスの規模やニーズに応じて最適なカードを選びましょう。契約時には、限度額や手数料率、支払い条件などを確認することが重要です。
2.支払いシステムの設定
クレジットカードを利用した請求書払いをスムーズに行うためには、支払いシステムの導入が不可欠です。まず、取引先がクレジットカード決済に対応しているかを確認しましょう。対応している場合は、取引先にカード払いの方法や手数料負担について確認し、必要に応じて支払いの条件を調整します。
取引先がカード払いに対応していない場合でも、代行サービスや決済プラットフォームを利用することで、請求書をクレジットカードで支払うことが可能です。これにより、取引先には従来通りの銀行振込が行われ、支払い側はクレジットカードの利便性を享受できます。
3.会計ソフトや経費管理ツールとの連携
請求書カード払いを導入したら、会計ソフトや経費管理ツールとの連携を図ることが業務効率化のカギです。多くのビジネス向けクレジットカードは、クラウド会計ソフトや経費精算システムと自動的に連携でき、カード利用履歴を取り込むことで、経理処理を自動化できます。これにより、手入力のミスや煩雑な帳簿作業を減らすことができます。
まとめ
本記事では、請求書のクレジットカード払いについてご紹介しました。クレジットカード払いを利用することで、支払いサイトを延長し、キャッシュフローを安定させることができます。
また、クレジットカードの利用によってポイント還元やキャッシュバックを受けることで、経費の節約や現金の還元といったメリットも得られます。
資金繰り改善の手段の一つとして検討されてみてはいかがでしょうか?
FUEL 編集部 TAKAHASHI
ターゲットメディア株式会社(2018年入社)運用ディレクター。
広告・マーケティング業界に特化したBtoBメディアの運用責任者を経て
育児のため一時休職。現在は、中小企業向けの情報サイト「FUEL」の運用に従事。