シャドーITによるセキュリティリスクと対策方法
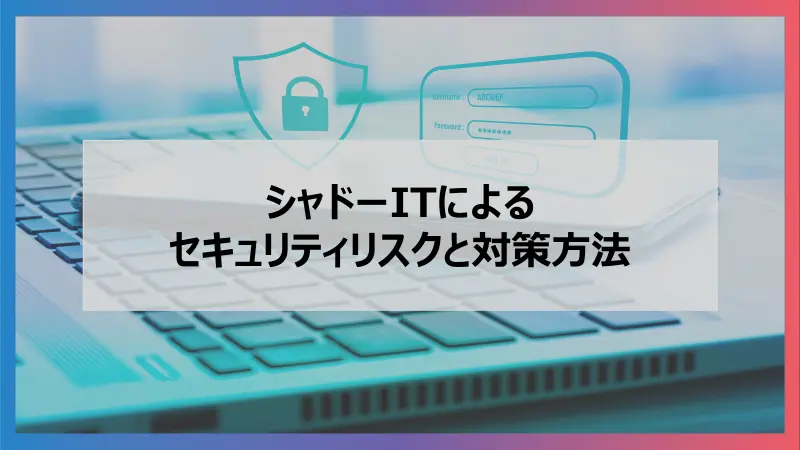
「セキュリティ対策は万端なのに、知らないうちに危険なシステムが使われているかも…?」、そんなご不安はありませんか?本記事では、企業にとって深刻な脅威となるシャドーITがもたらすセキュリティリスク、そして効果的な対策方法まで詳しく解説していきます。ぜひ自社のシャドーIT対策に役立ててください。
シャドーITとは?
シャドーITとは、IT部門の承認を得ずに従業員が導入・利用する情報システムのことです。従業員が業務で利用するIT機器やサービスの中に、企業が認識していないものが存在することがあります。このような状況は「シャドーIT」と呼ばれ、従業員が個人的な目的で利用しているSNSなどのSaaS、オンラインストレージといったクラウドサービス、または私用デバイスなどを、企業の許可を得ずに業務で使用している状態を指します。近年、シャドーITは情報セキュリティ上の懸念材料として注目されています。
シャドーITによるセキュリティリスク
シャドーITは、企業にとって深刻なセキュリティリスクをもたらす可能性があり、以下のような問題点が挙げられます。
システム環境構築におけるリスク
クラウドサービスの利用は、企業にとって利便性が高い反面、セキュリティリスクも伴います。従業員の不注意によるデータ漏えいや不正アクセスは、深刻な問題を引き起こす可能性があり、注意が必要です。特に、IDやパスワードの適切な管理、アクセス権限の設定ミスは、セキュリティ対策の観点から重要な課題となります。
チャットツール利用のリスク
近年、メールに代わるコミュニケーション手段として、チャットツールの利用が拡大しています。チャットツールは、メールよりも手軽に、そして迅速に意思疎通を図ることができる便利なツールとして、多くの企業で導入が進んでいます。しかし、企業が正式に契約したものではない、従業員個人が私的に利用するチャットツールは、セキュリティ上の懸念が生じる可能性があります。
企業は従業員が私的に利用するチャットツールにおける情報の内容を把握することができないため、企業にとって重要な機密情報が、従業員によって外部に漏えいするリスクがあります。さらに、従業員が会社を退職する際に、私的なチャットツール内の機密情報を完全に削除することが困難な場合もあり、情報漏えいのリスクは高まります。
喫茶店や空港など、第三者が周囲を容易に覗き見ることができるような公共の場において、私的なチャットツールを使用することは、機密情報漏えいのリスクをさらに高める行為と言えます。このような場所では、周囲の人々に会話の内容や画面の内容を覗き見られる可能性があり、企業にとって重大な情報漏えいに繋がる可能性があります。
Wi-Fi/無線LAN/ルーター接続のリスク
オフィス外での業務を行う際、セキュリティリスクを回避するためには、適切なWi-Fi環境を選択することが不可欠です。悪意のあるWi-Fiスポットは危険ですが、セキュリティ対策が不十分な無線LANルーターや、セキュリティレベルの低いフリーWi-Fiも、情報漏えいのリスクがあります。これらのWi-Fiに接続すると、業務で使用する重要なIDやパスワードなどが盗み見られる可能性があり、重大なセキュリティリスクとなります。
オンラインストレージでのデータ管理リスク
無料のオンラインストレージサービスは、セキュリティ対策が不十分な場合があり、個人情報漏えいのリスクがあります。企業で使用しているストレージから個人用のストレージにデータを移行した場合、コピーされた情報が漏洩する可能性も考えられます。
私用デバイス利用のリスク
業務に私用デバイスを使用する場合、セキュリティ対策が不十分な状態では、情報漏えいやマルウェア感染などのリスクが生じます。自宅で使用しているノートPCを社内ネットワークに接続すると、マルウェアに感染する可能性があります。また、機密情報を私用デバイスに保存しておくと、デバイスの盗難や紛失によって情報が漏洩する危険性も高まります。
フリーメール利用のリスク
無料で利用できるメールサービスは、手軽にアカウントを作成できる便利なツールですが、業務で利用する際には、セキュリティ面での懸念が生じることがあります。例えば、個人用の無料メールアドレスから取引先にメールを送信する場合、普段とは異なるアドレス帳やメールソフトを使用するため、誤って情報を送信してしまうリスクがあります。
シャドーIT対策
下記セキュリティ対策を講じ、シャドーITに起因するリスクを最小限に抑えることが可能です。
IT資産管理の徹底
企業ネットワークに接続されているすべてのデバイスやソフトウェアを把握し、管理下に置かないデバイスやソフトウェアの存在を明確にします。ネットワーク監視ツールや資産管理システムの導入が有効です。
明確なセキュリティポリシーの策定と周知徹底
IT資産の利用に関するルールを明確化し、全社員に周知徹底します。これにより従業員がセキュリティ意識を持ち、適切な行動をとるように促すことができます。
高度なセキュリティ対策ソフトの導入
ウイルス対策ソフト、ファイアウォール、侵入検知システムなど、最新かつ効果的なセキュリティ対策ソフトを導入することで、デバイスのセキュリティレベルを向上させることができます。
継続的なセキュリティ教育の実施
従業員に対してセキュリティに関する意識向上のための教育を定期的に実施し、最新の脅威や対策方法について理解を深めることが重要です。また、フィッシング詐欺やパスワード管理など、具体的な事例を交えながら、実践的なセキュリティ対策を学ぶ機会を提供することも有効です。
定期的なセキュリティ監査の実施
セキュリティ対策が適切に実施されているかを定期的に監査し、必要に応じて対策を見直すことで、常に最新の脅威に対応できる体制を構築する必要があります。
シャドーITの実態を把握する方法
企業におけるIT管理において、シャドーITの存在は無視できない課題です。この問題に対処するためには、まず社内調査を行い、現状を把握することが必要です。
従業員へのアンケートやインタビューを通じて、どのようなIT機器やサービスが利用されているのか、その目的や利用状況を調査します。この調査によって、シャドーITの利用状況や目的、規模などを明らかにすることができます。調査結果に基づき、業務に必要不可欠なシャドーITなのか、それとも業務効率を向上できる潜在的な可能性を秘めているのかを判断し、それぞれに適切な対策を検討する必要があります。
MDM導入によるデバイス管理
リモートワーク導入企業において、モバイル端末管理(MDM)はセキュリティ対策に不可欠です。MDMを活用することで、従業員が持ち出すモバイル端末を遠隔操作で管理できるようになります。具体的には、紛失時における端末のロックやデータ消去、機能制限の付与、ウイルス感染時の復旧など、様々な対策を遠隔から実施できます。これにより、場所を選ばずに安心して業務に取り組むことができる環境が実現します。
CASBによるクラウドサービスアクセス制御
企業がクラウドサービスを利用する際には、セキュリティ対策が欠かせません。特にCASB(Cloud Access Security Broker)は、企業にとって有効なセキュリティ対策手段と言えます。CASBを導入することで、社内におけるクラウドサービスの利用状況を詳細に把握することができます。さらに、マルウェアなどの脅威を検出し、不正なアクセスを遮断することで、社内外のアクセスを安全に管理することが可能になります。
例えば、従業員が許可されていないクラウドサービスにアクセスしようとした場合、CASBはそれを検知し、アクセスを遮断します。また、従業員がマルウェアに感染したデバイスからクラウドサービスにアクセスしようとした場合も、CASBはそれを検知し、アクセスを阻止します。このように、CASBは多岐にわたるセキュリティ対策を提供することで、企業のクラウド環境を安全に守ります。
まとめ
シャドーITは、セキュリティリスクを招きかねない一方で、従業員の業務効率化や働き方改革を促進する可能性も秘めています。企業は、シャドーITの実態を把握し、適切な対策を講じることで、安全な業務環境を実現し、従業員の生産性向上とイノベーションを促進することが可能になります。
FUEL 編集部 TAKAHASHI
ターゲットメディア株式会社(2018年入社)運用ディレクター。
広告・マーケティング業界に特化したBtoBメディアの運用責任者を経て
育児のため一時休職。現在は、中小企業向けの情報サイト「FUEL」の運用に従事。