情報セキュリティ教育の重要性と研修方法
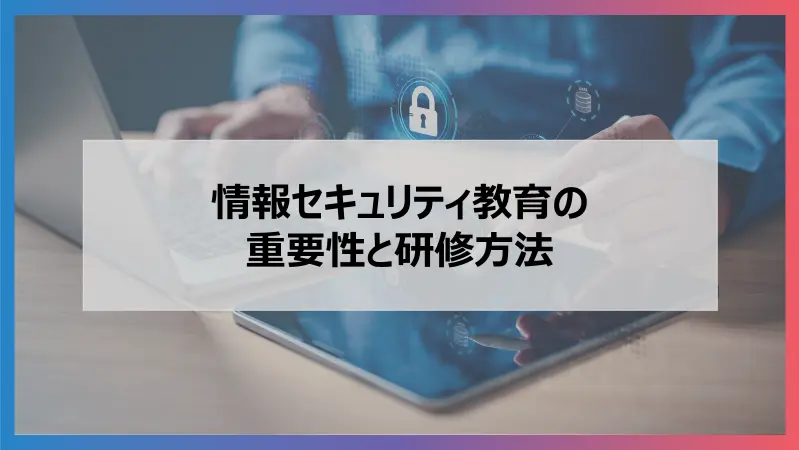
「情報セキュリティ対策は重要だけど、どこから手をつければいいか分からない」「自社の現状に合った教育方法が知りたい」そんな悩みをお持ちではないですか?本記事では、情報セキュリティ教育の重要性と実施方法について解説します。
情報セキュリティ教育とは何か?
情報セキュリティ教育は、従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高め、セキュリティ対策の知識を深める教育のことです。組織の安全を守るために不可欠な取り組みであり、情報漏えいやサイバー攻撃などのリスクを軽減することができます。
情報セキュリティ教育の重要性
中小企業経営者の多くは、自社のサイバー攻撃に対する脆弱性を過小評価していますが、実際には中小企業の5社に1社がサイバー攻撃による被害を受けているという統計があります。中には、被害額が1,000万円を超える事例も確認されています。
サイバーリスクは決して他人事ではなく、最悪の場合、予想外の大きな損害を被る可能性もあります。 経営者は、貸倒れリスクや自然災害リスクと同様に、サイバーリスクを経営上の重要な課題として認識する必要があります。
情報セキュリティを強化する3つの側面
サイバーリスクを低減し、情報セキュリティを強化するためには、オペレーション、システム、そして人間の3つの側面から対策を検討する必要があります。
①オペレーション面におけるセキュリティ強化
オペレーション面では以下の対策が効果的です。
- 定期的なセキュリティパッチの適用
- 脆弱性診断の実施
- アクセス権限の厳格な管理
- システム利用状況の記録と監視
- インシデント発生時の対応計画の策定
サイバー攻撃などのリスクを効果的に軽減するためには、情報セキュリティポリシーを策定しておくことが重要です。情報セキュリティポリシーは、組織の情報資産を守るための基本原則を定めたものです。情報資産の機密性、完全性、可用性を確保するためのルールを明文化し、従業員に周知徹底することで、セキュリティ意識の向上と行動規範の統一を図ります。また、情報セキュリティインシデント発生時の対応手順を明確化することで、迅速かつ適切な対応を可能にし、被害を最小限に抑えることができます。
情報セキュリティポリシーは、組織の規模や業種、扱う情報の重要度に応じて、適切な内容に策定する必要がありますので、専門家の意見を参考にしながら、自社の状況に合わせた情報セキュリティ対策を講じることをおすすめします。
②システム面におけるセキュリティ強化
システムセキュリティは、コンピュータシステムへの不正アクセスやデータ漏洩を防ぐための対策を指します。システム面では以下の対策が有効です。
- セキュリティソフトの導入
- ファイアウォールの設置
- VPNによる安全な通信環境の構築
- データの暗号化技術の活用
③人の意識におけるセキュリティ強化
人材面では、以下の対策が重要となります。
- 情報セキュリティに関する意識向上のための取り組み
- セキュリティに関する教育の実施
- アクセス権限の適切な付与
- パスワード管理の徹底
- 情報漏洩対策の強化
最も重要なのは「人」の意識改革
3要素の中で最も重要なのは、人間です。
どんな高度なシステムも、人間の指示なしには機能せず、どんなに厳格なルールやポリシーがあっても、人間が守らなければ意味がありません。そのため、従業員のセキュリティ意識とリテラシーを高めることは、情報セキュリティ対策において最も重要な課題となっています。日常的な啓蒙活動を含む情報セキュリティ教育は、従業員のセキュリティ意識向上を促すための最善の方法です。
効果的な情報セキュリティ教育とは
情報セキュリティ教育は、大きく分けて研修と、日常的な業務における啓蒙活動やフォローアップ、つまり現場での業務を通じた教育(OJT)の2つに分類されます。
研修は、多くの場合、情報システム部門または経営企画部門が主体となって実施されます。一方、OJTは、従業員同士の相互作用の中で自然発生的に行われるケースが多く、セキュリティ意識の高い上司の存在が、部下のセキュリティ意識向上に繋がり、組織全体のセキュリティ意識を高める効果が期待できます。このような好循環を生み出すためには、研修が重要な役割を担い、セキュリティ意識の向上を促進するきっかけとなります。
効果的に情報セキュリティ教育を実施するには?
情報セキュリティ研修の準備
効果的な教育を実施するためには、事前に綿密な計画を立て、対象者、実施時期、内容、形式などを慎重に検討する必要があります。
- 対象者: 研修の対象者は、機密情報へのアクセス権を持つ可能性のあるすべての人です。機密情報は、会社の財務情報や人事情報、顧客リスト、開発中の製品情報、製造工程情報など、多岐にわたります。重要なのは、機密情報には「個人情報」も含まれるということです。教育対象となる従業員の職種、レベル、所属部署、役職などを明確に特定し、それぞれの職種やレベルに合わせた内容で教育を実施することで、より効果的に理解を深めることができます。研修は自社の従業員だけでなく、必要に応じて契約社員や外部委託先の社員にも実施する必要があります。
- 実施時期: 新規入社時のオリエンテーション、定期的な研修プログラム、セキュリティインシデント発生後の緊急対策など、組織の状況に合わせて適切な時期を設定することが重要です。新入社員に対しては、入社時に情報セキュリティに関する基本知識を身につけさせることで、セキュリティ意識の向上を図れます。セキュリティ研修は、定期的なものと不定期なものの2種類があります。定期的な研修には、毎年全社員対象に実施するセキュリティ研修や、新入社員向けのセキュリティ研修などがあります。全社員向けの研修では、実施時期を慎重に検討する必要があります。研修の目的は、組織再編や人事異動によってセキュリティ意識やセキュリティリテラシーがばらばらになった状況において、研修を通じて社員の意識を統一し、共通認識を持たせることです。
一方、定期研修を補完するのが、随時行われる不定期研修です。不定期研修は以下場合があげられます。
- 同業他社でセキュリティ事故が発生した場合
- 自社でヒヤリハットや事故が発生した場合
- セキュリティポリシーが変更された場合
- 新たな種類のウイルスが出現した場合
- 内容: 情報セキュリティに関する基礎知識、情報漏洩対策、不正アクセス対策、パスワード管理、社内ネットワーク利用、ソーシャルメディア利用など、対象者の職務内容や組織の課題、セキュリティリスクなどを考慮して適切な内容を選択します。また、最新の情報セキュリティ脅威や対策に関する情報も盛り込むことで、実践的な知識を習得することができます。
- 形式: 対面式研修、オンライン研修、eラーニングなど、様々な形式が考えられます。対面式研修では、講師との質疑応答やグループワークを通して、参加者同士の理解を深め、活発な議論を促進することができます。オンライン研修は、時間や場所の制約を受けずに受講できるメリットがあります。eラーニングは、個々のペースで学習を進められるため、効率的に知識習得が可能です。それぞれの形式の長所と短所を比較検討し、組織の状況や目的に最適な形式を選択することが重要です。
関連記事:企業向けセキュリティ教育を強化するためのeラーニング活用のすすめ - その他: 研修資料の作成、受講者の事前準備、事後評価など、教育効果を高めるための様々な準備が必要です。わかりやすく、実践的な内容の研修資料を作成することで、受講者の理解を深めることができます。受講者には、事前に研修内容に関する予習や準備を促すことで、より積極的に参加を促すことができます。事後評価を実施することで、研修の効果を検証し、今後の教育内容や方法の改善に役立てることができます。
これらのポイントを踏まえて、組織の状況や目的に合わせた情報セキュリティ教育を計画し、実施することで、従業員のセキュリティ意識を高め、情報セキュリティ対策を強化することができます。
研修形態の種類と実践方法
研修形態には内部と外部の2種類があります。組織内部のリソースを活用して研修を実施するのか、それとも外部企業に委託するのかは、企業にとって重要な選択事項です。
自社で情報セキュリティ研修を行う場合
情報システム部門や情報セキュリティ担当者など、社内に専門人材がいる企業であれば、これらの担当者を講師として活用することで、社内での研修開催が実現可能です。自社内での研修開催は、研修内容をより実務に即したものにすることができ、外部講師を招く場合に比べて講師費用を抑えられるというメリットがあります。
しかし、社内担当者が研修を担当することで、本来の業務遂行が阻害され、結果的にコスト増につながる可能性も考慮する必要があります。
教材|社内資料、外部資料を効果的に活用する
企業がコンテンツを作成する際、すべてを自社で制作する必要はありません。例えば、様々な資料が揃っているデータベースを活用することで、自社教材の参考資料を探す際に役立ちます。
講師|専門知識がなくてもよい
企業内でのセキュリティ教育担当者は、必ずしもセキュリティの専門家でなくても構いません。重要なのは、セキュリティ意識、リテラシー、ポリシーの周知を効果的に促進できることです。セキュリティ意識の向上を目的とする場合、専門知識よりも、分かりやすく説明できるコミュニケーション能力や、社内での影響力を持つ人物が適任です。
内容|多様なテーマを組み合わせる
情報セキュリティの重要性を理解し、具体的な対策を講じるためには、様々な側面から学ぶ必要があります。例えば以下のようなテーマが挙げられます。
- セキュリティポリシーとルール
組織における情報セキュリティの基盤となります。これらのポリシーとルールは、情報資産へのアクセス、利用、管理に関する明確なガイドラインを提供し、セキュリティ事故のリスクを低減します。
- セキュリティ事故発生時の対応方法
事前の対策だけでなく、万が一事故が発生した場合の迅速な対応が求められます。事故発生時の対応手順を事前に定め、関係者への連絡体制や情報共有、損害の最小化などをスムーズに行う必要があります。
- セキュリティ事故の事例
潜在的な脅威を理解し、対策を強化するために重要です。過去の事例から教訓を得て、自社の状況に合わせて対策を検討することが求められます。
- セキュリティリテラシー向上
従業員一人ひとりの意識改革が不可欠です。セキュリティに関する知識や意識を高め、情報セキュリティに関するルールを遵守することが重要です。
- 情報セキュリティのトレンドの把握
最新の手法や脅威に対応するために重要です。新しい技術や攻撃手法の出現、セキュリティ対策の進化などを常に追いかける必要があります。
- 業種別のセキュリティ情報の収集
自社の業務特性に合わせた対策を検討することが重要です。例えば、金融機関では顧客情報の保護が重要となる一方で、製造業では製造設備のセキュリティ対策が重要となります。
- 個人情報の保護
個人情報保護法などの法令に基づき、適切な対策を講じる必要があります。個人情報の収集、利用、提供に関するルールを遵守し、プライバシーの保護に努める必要があります。
情報セキュリティの講義では、受講者のレベルや扱う情報の性質に応じて、これらのテーマを適切に組み合わせて、効果的に学習を進めることが重要です。
標的型メール訓練|実践的な教育方法
標的型メール訓練は、従業員に対して、あたかも外部からの攻撃者から発信されたかのようなメールを送り、その反応を分析するものです。 この訓練を通じて、従業員は攻撃メールに対する警戒心を高め、安全な行動を習得することができます。 メールを削除したり、セキュリティ担当者に報告したりした従業員は、高いセキュリティ意識を持っていることを示します。 逆に、メールを開封し中のリンクをクリックしてしまった従業員は、セキュリティ意識が低いことを示すため、セキュリティ研修の受講を推奨します。 標的型メール訓練は、従業員のセキュリティ意識の向上に貢献するだけでなく、必要な教育を必要な従業員にのみ提供できるという利点があります。
情報セキュリティ研修を外注する場合
外部委託の場合、公開講座への参加、外部講師のアテンド、外部eラーニングサービスの契約など、複数の選択肢があります。外部委託は、社内担当者の負担を軽減し、研修内容の正確性と網羅性を確保できるという利点があります。また、外部の専門家を活用する研修には、企業のニーズに合わせた個別対応が可能な「1社向け研修」と、複数企業が参加する「公開研修」の2つの形式があります。以下ではそれぞれの特徴と費用について詳しく解説します。
1社単独の研修
1社向け研修は、企業独自の課題や目標に特化したカリキュラムを構築できる点が大きなメリットです。社内情報や機密情報を含む内容も研修に取り入れることができるため、企業にとって非常に有効な研修形式と言えます。さらに、担当者と密接な連携を図りながら研修を進めることで、より効果的な学習を促進できます。しかし、費用面では公開研修よりも高額になる傾向があります。研修内容、時間、講師の費用などによって費用は変動しますが、企業の規模やニーズによっては、費用対効果の高い選択肢となります。
複数の企業が参加する公開研修
公開研修は、参加費を抑えられる点がメリットであり、同じ業界の他の企業と交流する機会も得られます。標準的なカリキュラムで構成されているため、短期間で効率的に必要な知識やスキルを習得できます。
公開研修の費用も、研修内容、時間、講師の費用などによって変動しますが、一般的に1社向け研修よりも安くなります。費用を抑えつつ、最新の知識やスキルを習得したい企業にとって、有効な選択肢となります。
上記以外にも、オンライン研修など、さまざまな研修形式があります。企業の規模、ニーズ、予算などを考慮し、最適な研修形式を選択することが重要です。
まとめ
情報セキュリティ教育は、組織全体でサイバーリスクに対する意識を高め、安全な情報環境を構築するために欠かせません。研修を通じて従業員は、セキュリティ対策の重要性、具体的な脅威、そして日々の業務における適切なセキュリティ対策を理解することができます。また組織の競争力強化、顧客や取引先からの信頼獲得、そして事業継続性を確保するために不可欠です。効果的な情報セキュリティ教育を導入することで、組織はサイバー攻撃から身を守り、安全で安定した事業運営を実現することができます。
FUEL 編集部 TAKAHASHI
ターゲットメディア株式会社(2018年入社)運用ディレクター。
広告・マーケティング業界に特化したBtoBメディアの運用責任者を経て
育児のため一時休職。現在は、中小企業向けの情報サイト「FUEL」の運用に従事。